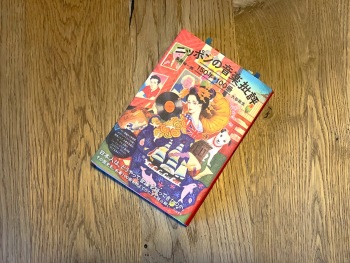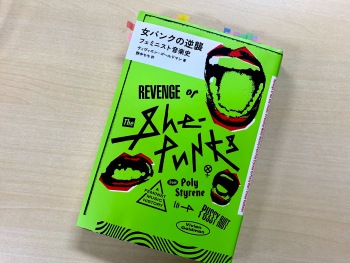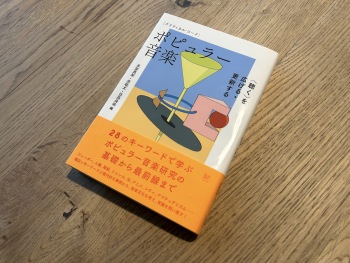“ロックンロール宣伝マン”が綴る、稀代のロック・ミュージシャンの実像と魅力──書評 : 高橋康浩著『忌野清志郎さん』
オトトイ読んだ Vol.27

オトトイ読んだ Vol.27
文 : 岡本貴之
今回のお題
『忌野清志郎さん』
高橋康浩 : 著
ele-king books : 刊
出版社サイト
OTOTOYの書籍コーナー“オトトイ読んだ”。今回は忌野清志郎に関して高橋康浩がその存在について綴った1冊『忌野清志郎さん』。高橋康浩は、1988年の『COVERS』発売直後の混乱期、『コブラの悩み』~ザ・タイマーズ~RCサクセションの解散という、忌野清志郎のキャリアにおいても特に激動の時代に、その近くで宣伝担当としてともに働いた人物だ。ファンのあいだでは清志郎命名による高橋ROCK ME BABYというネームでも知られている。今回は、2018年にOTOTOYにて、高橋も含め、忌野清志郎に縁のある、もしくは大きな影響を受けた人々へと取材を敢行した連載『〜I LIKE YOU〜忌野清志郎』(後に加湿され『I LIKE YOU 忌野清志郎』として書籍化)を執筆したライター、岡本貴之による書評でお届けする。(編集部)。
“ロックンロール宣伝マン” 高橋康浩
──書評 : 高橋康浩著『忌野清志郎さん』──
文 : 岡本貴之
『忌野清志郎さん』の書影を最初に見たときに、ほんの一瞬だけ高橋さん自身の写真なのかと思った。よく見ると全然違うのだけれども(すいません)、清志郎ばりの派手な衣装を着てアジテーションを行ったりする“高橋Rock Me Baby”とは違い、普段はじつに穏やかで飄々とした素顔の高橋さんが、なんとなく自分の中でイメージとしてこの写真と重なったのかもしれない。そんな高橋さん初の著作『忌野清志郎さん』は、ときに“ロックンロール宣伝マン”として、ときに純粋な音楽リスナーとして、リスペクトを込めてしかし神格化することなく、稀代のロック・ミュージシャンの実像とその魅力が綴られている。
少し、自分と高橋さんとの関係について紹介させてもらいたい。出会ったきっかけは、じつは本稿が載っている「OTOTOY」だった。2015年、「オトトイの学校」というカルチャー講座シリーズで行われていた「パブリシスト養成講座」に、当時OTOTOYの副編集長だった西澤裕郎氏に誘われて参加したときのことだ。当日になって足を運んでみると、講師を務めていた渡邊ケンさんが思いもよらないゲストを呼んだ。それが、高橋さんだった。
当然、ゲスト講師として登壇することは発表されていたはずだが、自分はそのことを把握しておらず、高橋さんを見て「あっ!清志郎のイベントによく出てくるあのド派手な格好の人だ!」と思った。清志郎の没後に行われていたイベントのMCとして、何度もそのお姿を拝見していたし、かつて東芝EMIの宣伝担当だったことも知っていた。「こんな機会はめったにない」と思った私は、講座が終わると高橋さんを掴まえて、いかに自分が忌野清志郎ファンであり、OTOTOYでRCサクセションの曲「多摩蘭坂」をもじった「たまらんニュース」という連載記事も書いていることをまくしたてた。すると、高橋さんはその5倍ぐらいの熱量で、清志郎について語り始めた。ライター業を初めて3年ぐらいしか経っていなかった自分にとって、あの忌野清志郎のそばで仕事をしていた人と話せるなんて、夢のような気分だった。とはいえ、その場にはたくさんの講座生がいたこともあって、名刺交換をして、後日改めて話を訊かせてもらうことを約束した。
その日から現在に至るまで、高橋さんには幾度となく取材して記事を書いたし、普段もいろんなことを教えてもらっている。拙作『I LIKE YOU 忌野清志郎』(河出書房刊)のもとになったWEB連載を始める際には、ご本人へのインタビューはもちろん、様々な関係者への橋渡しでご協力もしていただいた。自分にとっては恩人のひとりだ。
シニカルさと純粋な親しみやすさ―忌野清志郎の両極端な表現
『忌野清志郎さん』の前半は、高橋さんが初めて忌野清志郎率いるRCサクセションのライブを観た瞬間から、RCの最終作品となったアルバム『Baby a Go Go』までの日々の回想とが綴られている。高橋さんといえば真っ先に浮かぶのが、やはりRCのアルバム『COVERS』発売中止やタイマーズが起こした「FM東京事件」など、清志郎にとって最も激動な時期に宣伝担当者として、行動を共にしていたことだ(入社したのは『COVERS』発売中止の後とのこと)。高橋さんはその当時の出来事については、様々な媒体で折に触れてきたし、書籍だからといって特に目新しい話はないのかなと思っていた。ところが、この本で初めて知ったことがあった。それは、「FM東京」の放送禁止用語を交えた歌詞や騒動に、高橋さんがショックを受け心を痛めていたということだ。当時のあれこれについて話を訊くとき、こちらはついつい面白おかしい感じで話題にしてしまうのだが、高橋さん自身はタイマーズのセンセーショナルな存在を決して面白がっていたわけではなかった。タイマーズのアルバムには良い曲があることを認めながらも、好きになれない部分もあり、「これを売らなければいけない」という宣伝マンとして立場との葛藤を抱えながら、日々の激務に奔走していたという。そんな葛藤の中、そうした刺激的なタイマーズの印象と対を成す曲「デイ・ドリーム・ビリーバー」について、「この曲があったからがんばれた」と語っていることは、なんだかとても救われた。人を傷つけるような言葉を使ったり毒舌を吐いたりするシニカルさと、素朴で純粋で、孤独な心情に寄り添う言葉と親しみやすいメロディ。高橋さんは、そういうことを伝えたくて書いたのではないかもしれないが、その両極端な表現力で以って、良くも悪くも人の心を揺り動かす音楽を世に送り出し続けた忌野清志郎というアーティストの音楽とキャラクターを、端的に表しているエピソードだと思う。
RCサクセションについてのマニアックな視点
第二章「RCサクセション」以降は、清志郎のみならずRCのメンバーの演奏スタイルなどにも触れながら、そのときどきの言動、エピソードから、影響を受けているミュージシャンや、音楽性を深く掘り下げている。「雨あがりの夜空に」のイントロでチャボ(仲井戸麗市)が弾きやすい5弦5フレットのDコードではなく6弦10フレットルートのDでギターを弾くことなど、マニアックな視点での考察が面白い。
第三部「ローランド・カークはとっくに死んでいる」では、清志郎との会話を通して様々なアーティストの存在を知ることでさらに清志郎の音楽について興味を抱いていったこと、音楽知識を深めていったのであろうことが伺える。また、高橋さんは度々、「忌野清志郎はレコーディング・アーティストであり、ライブはパーティのようなものだと思っていたのでは」と語っている。編者の野田努氏との対談「あとがきにかえて」の結びでも話しているように、「ソングライターとして、レコーディングアーティストとしての忌野清志郎とその作品」について、まだまだ語りたいこと、伝えたいことはあるはずだ。
「清志郎さんは僕にとって、あのRCサクセションのリード・シンガーであり、ロックンロール・スターです」との言葉どおり、高橋さんの気持ちは何年経っても、初めてRCサクセションのライブを観たときのままなのだろう。2020年のRCサクセション・忌野清志郎 デビュー50周年を機に、毎年リリースされているベスト盤や過去作のデラックス・エディション、初アナログ化作品など、情熱と純粋な思いを原動力に、高橋さんは今なお最大のリスペクトを込めて、「清志郎さん」の音楽を世に伝え続けている。