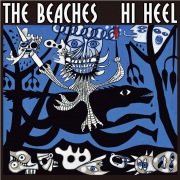ビーチズの新作『ハイヒール Hi Heel』が素晴らしい。いや、ビーチズの作品はこれまでも素晴らしかったし、言うなればジェリー・リー・ファントムの時代から彼らは常に素晴らしいダンス・ミュージックを演奏し続けていたのだが、ここに来てやっとメディアの評価も追いついてきたという印象だ。全く、遅いっつーの。本作の背景にあるのは、まず国内外における非欧米的な音楽の流行。これまでも中南米、アフリカ、アジア、東欧など、貧欲に世界中のあらゆるビートを吸収してきたザ・ビーチズの音楽が、遂に時代と合致したのだ。また本作からはそういった世界中の音楽に接することで改めて浮き彫りになった、世界の中で音楽を奏でる日本人という、自らのアイデンティティを再確認する作品となっていることが素晴らしい。くるりがクラシックをはじめとした世界中の音楽に触れる中で、やはり自らのアイデンティティを再確認し、京都音楽博覧会という場で実践していることを、ビーチズはもっと享楽的に、祝祭的に鳴らしているというわけだ。ビーチズのライブ、ホント最高だからみんな行ったほうがいいと思うよ。インタビューでは新作についてはもちろん、昨年末のジェリー・リー復活についてや、国内のロック・シーンについても話してもらい、充実の内容になったと思う。
インタビュー&文 : 金子厚武
INTERVIEW
—昨年一年はアルバムを作る気にはならなくて、ファーストとセカンドの曲を中心にもっとライブをする必要があったとのことですが、それはなぜだったのでしょう?
ヒサシ the KID(以下、H) : 最初からなんとなくのイメージであったんだけど、06年にビーチズを始めて、翌年にはセカンドが要るだろうっていうのはあって、でもサードも立て続けに出すっていうのはなくて。ファーストとセカンドは納得のいく作品ができたから、まだ次のモードに行くまでに伝えなきゃいけないことがたくさんあるなって感じて。ライブをまわしていくために何かしらアイテムが欲しいなってことで、シングルは頑張って作ったんだけど、アルバムは急いで作ることもないなと思って。
—周りの状況もできてないし、自分たちとしてもやりたいことが見えていなかった?
H : こうゆうアルバムにしたいって言葉で出なくても、ちゃんと次のモードにバンド全体が行くと、セッションの中で“あ、こうゆうアルバムになるんだ”ってイメージがその場で生まれたりするから。ファーストの頃とかはやりたいことがはっきりしてたから、このコードは使わないって決まりごととか作って、それを楽しめてたんだけどね。
—アルバムを作ろうというモードに変わったのが今年の年明けごろ?
H : ですね。ライブを重ねていくうちに、“こうゆう曲欲しいな”とか“こうゆう場面がもっとあってもいいな”とか気づいてきて。あとは普段聴いてるものの影響で、“もう、これはないな”とか“この雰囲気はまだありかも”とか、そうゆう外からの音楽的な刺激もあったし。

—国内外でいわゆる非欧米的な音楽の波が起きている中で、ビーチズ的な音楽が受け入れられる土壌ができてきているという感触ってありましたか?
H : それはね、なんとなく雰囲気を感じてはいるんだけど、実際作ってるときには全く考えてない。これまでもそうなんだけど、状況ができあがるのを待ってる余裕もなければ、暇もないし。ただそうは言っても、ファーストとセカンド作ってライブやってきた中で、海外から似たような感覚を持ってやってるんじゃないかっていうバンドがたくさん出てきたのには勇気づけられたし、刺激にもなった。まあバンドよりかは、俺パーティーばっかり遊びに行くから、好きな人のDJとか、パーティー感だったり、そうゆうところでビーチズ的なことがアリなんじゃないかって、小さな世界だけど感じてはいたかな。
—1曲1曲がものすごくハイブリッドで、もはやジャンルも国も関係ないといった感じなのですが、本作の制作中に特にインスピレーション源になった音楽ってありましたか?
H : 今回が一番これっていうのはなかった。ファーストやセカンドの方がはっきりあって、例えば、どこでも言ってるけど最初はM.I.A.があったし、それにつながるゲットーなダンス・ミュージックがあって、それをバンド・サウンドで、日本語の歌を乗っけてやるっていうのが元々のアイデアだったから。それから色んなビートにチャレンジしてきて、去年末から今年頭って“今これだろ”みたいのが特になくて、もう俺のほうがおもしれえんじゃねえかぐらい思って。
—そもそもなぜ近年のヒサシさんは非欧米的な音楽により惹かれるようになったのでしょう? もちろんクラッシュしかり、昔からそうゆう音楽への傾倒はあったと思うのですが。
H : なんだろうなあ…気づいちゃったっていうのがデカイ気がする。00年代入ってすぐぐらいの頃のジェリー・リーは、すごく意識的にハウスとか、そうゆうダンス・ビートを取り入れて形にするってことをずっとやってたんだけど、そのときはその形が一番上手くいったから、たまたまそのビートだったってだけで。今のメンバーになったときに、特にトモ君が入ったのが大きいと思うんだけど、できることが広がったときに、やっとやりたいことができるようになったっていうか。昔から核になってるものはあんま変わんないから、結局昔のとか聴いてみても、そうゆうことがやりたかったんだろうなってわかる(笑)。
—バンドの変化と、シーンの流れが合致した?
H : だと思う。俺わかりやすいからM.I.A.って言ってるだけで、その前からポイントとなるような刺激ってあったんだけどね。コーナーショップの“ハンドクリームなんとか”(『Handcream For A Generation』(02))ってあったじゃん? あれとかすごくデカくって。さかのぼればずっとそうで、ベックの「Loser」とかもそうゆう印象で捉えてたし、クーラ・シェイカーとかストーン・ローゼズとか、やっぱりちっちゃいロックンロールだけの世界でやってる音楽じゃなくて、もっと色んなところにアンテナ張ってるバンドが昔から好きだし。ただあのタイミングでM.I.A.が出てきたときに、もっと思い切ってやれることがあるはずだって明確に思ったのは確かなんだけどね。
—世界中のあらゆる音楽に触れることで、逆に自国の音楽に対する理解も深まるという側面がありますよね。本作では歌謡曲がインスピレーション源の一つだったとのことですが、こういった文脈と関係していますか?
H : 歌謡曲的なことをやろうとしてそうなったわけでは全くなくて、色んな国の音楽を聴いて、そのメロディに影響を受けて、日本語で歌ってみたときに、なんかこれ歌謡曲っぽいなって思ったっていうだけ。あと当時の歌謡曲って一つ一つのリフが大げさで、笑えたりするから、それに負けないぐらい大げさでいいんじゃないかなって。みんなにちゃんとポップな形で聴こえるようにするには、すごくメロディアスにするとかじゃなくて、どこか極端に振り切ることが大事だっていつも思ってるから、その一つのアイデアとして、歌謡曲的な、大げさでばかばかしい、勘違いというか…
—情報の共有がなかったがゆえの面白い勘違いがあったわけですよね。
H : そうそうそう。でも今も実際あるとは思うんだよね。やっぱり世界中の音楽聴いてるって言っても、現場に行ってるわけじゃないから。全く違う解釈でやってると思うし、でもそれが絶対個性になるはずだから。
—リリックに関してはどうですか? ストリートで暮らす若者の光景が基本にあると思うのですが。
H : あんまりリアルっていうのを言葉で書こうとは思ってなくて、旋律との距離感って言うか、ある旋律に言葉を乗せることで、それがリアルに聴こえないっていうのが面白いんだよね。バーンって曲が鳴ったときに、“ああ、わかるわかる”っていうよりかは、やっぱりどっか飛べるような感覚であって欲しいっていうか、リアルというよりファンタジーな感じがした方がいいなと思ってて…もうわかってることを書きたくないんだよね。そんなこと言われなくてもわかるよってことを言われても、そこに音楽の楽しさがある気はしないから。一瞬リアルに聴こえるような歌詞でも、そうじゃなく聴こえるような楽曲であってほしいし、すごくリアルな街の匂いを伝えるようなトラックだったら、逆に全く関係のないことを書くかもしれないし、そうゆう距離感がいつも大事。
—ヒサシさん自身の体験が根底にあるとは言えますか?
H : …なくはないだろうね。具体的なエピソードがあるかって言ったら全くないけどね。どうゆうところであるかって言ったら、とにかくクソすることねえっつうか、何もない田舎で育ってるし、その退屈さったらないっていうさ。あと10代の頃とか、もっとどんよりした世界感に惹かれるところがあって、今の10代の子たちがどんな音楽聴いてるのかわかんないけど、まあでも実際にはトップ10に入るような音楽だったりするわけじゃないですか? そう思ったときに、俺は10代の頃にああゆう言葉が欲しかったわけじゃなくて、別に寄り添って欲しかったわけじゃないっていうか、もっとぶっ飛んだことだったり、知らない世界を見たかった。中学生でパンクに出会ったときもそうゆうことだと思うんだけど、普段学校に行ってるだけでは見えてこない部分があったから惹かれたわけで、実際このアルバムもそうゆうアルバムだと思うし、そこを背伸びして聴いて欲しい。願いなのか何なのかわかんないけど。
—昨年末にジェリー・リー・ファントムで一夜限りのライブをしましたよね? 基本的にはジェリー・リーの10周年ということで、メモリアルなものだったと思うのですが、あれをやったことによって見えたこともあるのではないかと思うのですが?
H : 自分でもびっくりするぐらい違うバンドだった(笑)。新たな発見みたいなことはなかったかな、ただホントに違うバンド組んだんだなって思った。よく“改名”って書かれちゃうんだけど、俺一言もそんなこと言ってないから。俺ジェリー・リーやめたとも言ってないし、新しいバンド組んだんだっつってるだけで。まああまりにも違ったから、(ビーチズとして)何を頑張ってきたのかはわかった。あまりにも緊張感もノリも違うから、メンバー4人顔見合わせて笑っちゃったもん(笑)。
—当時“気づいたら乗っ取られてた”っていう表現をしていたのがすごく印象的で、つまりは理屈ではないってことだと思うんですけど、今改めて振り返ると、この“乗っ取られた”という表現を別の言葉で表せますか?
H : そうだねえ…でも今思っても、やっぱり乗っ取られたんだと思う(笑)。いきなり海賊来てとりあえず楽器渡したみたいな(笑)。つってもどっちも俺だからね。
—地続きな部分もあるし…
H : 全然あると思うんだけどね。あのベーシックがなかったら、いきなりビーチズみたいな音楽絶対にできないから。
—国内のシーンについても聞いておきたいんですけど、今まさに“ロックとダンス”がキーワードになっていますよね? それってまさにジェリー・リー〜ビーチズがやってきたことなわけですが、ヒサシさんから見て、今のシーンってどう思います? 面白くなってきた? それともしっくり来ない?
H : まあ…そうね…大半つまんないと思ってる、実際には。ただ悪くないとも思ってる。難しいとこだけど…ダンスとかロックとかって言葉自体が俺の中にないからね(笑)。俺はロックンロールは全部ダンス・ミュージックだと思ってるし、俺の中でレゲエもヒップホップも何でも全部ダンス・ミュージックだって最初からそうゆう発想だから。ダンス・ロックって…ねえ(笑)。そんなかで俺たちみたいな、日本で生まれて音楽やろうってなったときのコンプレックスとかハンデって実際あると思ってて、俺の中には最初からロックンロールなんてないし、レゲエのビートもラテンのビートも何もないんだって所で、どうゆうビートだったら一番使いやすいかってところで、当時は四分のビートだった。キック四分で打って絡んでくってことは、どのジャンルでも対応できるからやってただけで、ロックとダンスの融合なんてハナから頭になかったから。そこがすごく上っ面になってると思う。肝心なのはその四分のビートにどうやってベースが絡んで、上のシンセが絡んでってことで、8ビートでやっても変わらないようなことが乗ってるだけだなって思うことが大半だから。踊れねえなあ、みたいな(笑)。
—確かにロックとダンスって言葉自体がちょっと安易ではありますよね。
H : 俺の周りにはロックンロールのいいバンドが多くて、ロックンロールに敵うためには俺たちどうすればいいだろうって発想だったから。ニートビーツだったり、当時はミッシェルがすごく大きかったから、そこへの反発心というか、もっと違うビートであれよりも踊れる曲をやるにはどうすればいいんだろうって頭悩ませてたのを覚えてる。
—ロックンロールへの愛情とその裏返しの反発心があって、先ほど言っていた日本人として何もないところから音楽をやるという意識もあって、だからこそ、その自分にないものややれないことを一つ一つ分析していった結果、今のビーチズは日本人にしか作りえない本当にオリジナルな音楽を作ることができたんでしょうね。
H : ああ、嬉しいですね。まあでも、それしかやることないんだよね(笑)。やれないこともわかってるし、やれるかもしれないこともわかってるし。最初はわからなかったけど、今の俺たちにはわかってるし。
—では最後に8/23に江ノ島で開催されるレギュラー・パーティー“DISCO SANDINISTA”のスペシャル版の魅力を語ってください。
H : 単純にビーチでビーチズやろうっていう、それだけのことで(笑)。“DISCO SANDINISTA”ってパーティーは、このアルバムにとってもすごく大事なパーティーで、あれがなかったらこうなってなかったから。普通のロック・バンドがやってるパーティーとは全然違うと思ってるし。やっぱ踊りに行かないやつがやってるパーティーとか、嘘臭くて全然行く気しねえっつうか、やっぱりみんなパーティー好きで、色んなところに遊びに行くような人たちだけでやってるパーティーだから、楽しいに決まってるよね(笑)。

THE BEACHES DISCOGRAPHY
POLICE & GIRLS & BOYS
2008年リリースのシングル。キャッチーかつまとわりついて離れないメロディが魅力の、踊れるロックンロール・チューン。『Hi Heel』にはアルバム・ミックスが収録されています。
HANA HOU
Disco, New Wave, Reggae, Punkなどあらゆるジャンルを飲み込んだRockでフロアのオーディエンスをDance Peopleに変える彼らの、2nd Album『HANA HOU』を「WESS RECORDS」より再発。RISING SUN ROCK FESTIVALにも出演が決定している「THE BEACHES」の傑作を再びここに。
LIVE SCHEDULE
DISCO SANDINISTA! Summer Special 2009
- 8月23日(日)@ 江ノ島KULA RESORT
DJ:村 圭史(FREAK AFFAIR)/ ヒサシ the KID(THE BEACHES)
GUEST DJ:露骨キット / タカラダミチノブ
OPEN・START 14:00 / END 21:00
入場無料
THE BEACHES Tour 2009「波に乗りたい〜ハイヒール Hi Heel 編〜」
- 10月12日(月)@ 鹿児島SR HALL
- 10月13日(火)@ 福岡DRUM SON
- 10月15日(木)@ 岡山CRAZYMAMA 2nd Room
- 10月16日(金)@ 大阪十三ファンダンゴ
- 10月17日(土)@ 名古屋CLUB UPSET
- 10月24日(土)@ 下北沢GARDEN
PROFILE
THE BEACHES
THE BEACHES[ヒサシ the KID(Vo・G)/dij(Dr)/r.u.ko(key)/TOMOTOMO club(B)]2006年に結成されたTHE BEACHESはDisco、New Wave、Reggae、Punkなどあらゆるジャンルを飲み込んだRockでフロアのオーディエンスをDance Peopleに変える。2006年5月に1st ALBUM『THE BEACHES』を発表し多くのメディアに注目を浴び、音楽誌「SNOOZER」の2006年ベスト・アルバムにランク・インした。そして何よりも彼らの魅力はライブにあり、2006年のデビューから様々なイベントに出演し、オーディエンスはもとより共演したアーティスト達からも絶賛され、各会場を真夏にする彼らのライブは必見。そして、2007年7月に待望のセカンド・アルバムを発売し、初のワンマン・ライブ・ツアーを行いさらに注目を集める。 2008年3月にはNY〜LAまで7都市でのUS Tourを行いアメリカにビーチズ旋風を巻き起こす。同年の夏FUJI ROCK前夜祭、RISING SUN ROCK FESTIVALに出演し、オーディエンスを大いに沸かす。
- THE BEACHES web : http://www.thebeaches.jp/
CLOSE UP : クラムボン
CLOSE UP : ジャック達
CLOSE UP : Anathallo
CLOSE UP : neco眠る