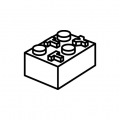芳垣安洋率いるOrquesta Libre、スタジオ・アルバムを2作同時リリース

ROVOや大友良英ニュー・ジャズ・オーケストラのドラマーとして活動し、豊かな経験と音楽感を持つドラマー・芳垣安洋が率いる大所帯バンド、Orquesta Libre。「さまざまなジャンルのスタンダード・ナンバーを片っ端からやってみる」というコンセプトを掲げ、自由でのびのびとした演奏をライヴを中心に聴かせてきた彼らが、待望のスタジオ・アルバムをリリース!! '60~'70年代のロックやポップス、演劇舞台音楽、ミュージカルや映画音楽、ジャズ・チューンから第三世界の音楽まで、邦楽/洋楽のスタンダード・ソングを“うた”と“インストゥルメンタル”でプログレッシヴに再定義する10人の楽団員と、ゲスト・ヴォーカリスト2人からなる、どこか不穏でそのくせキュートなオルタナティヴ吹奏楽団の音楽を、芳垣安洋の全曲レビューとともにご堪能ください!!!
オルケスタ・リブレと柳原陽一郎とおおはた雄一 ~plays standards Chant version / うたのかたち ~ UTA NO KA・TA・TI
Red Disc オルケスタ・リブレと柳原陽一郎
1. アラバマ・ソング / Alabama Song
2. ジゴロのバラード / Die Ballade von der sexuellen Hörigkeit
3. モリタート / Die Moritat von Mackie Messer (The Ballad of Mack the Knife) (live ver.)
4. 「人間はどうやって生きてきたのか?」 三文オペラ第2のフィナーレ / Ballade über die Frage Wovon lebt der Mensch (2nd Finale of Threepenny Opera)
5. いつもさよならを / Ev’rytime We Say Goodbye
6. アルフィーのテーマ / Alfie
7. スマイル / Smile
Yellow Disc
オルケスタ・リブレとおおはた雄一
1. いとしのセシリア / Cecilia
2. ゴロワーズを吸ったことがあるかい
3. リリー・マルレーン~青い旅団 / Lili Marleen~including ”the Blue March of Turkey”
4. オー・シャンゼリゼ / Les Champs-Elysees
5. パープル・ヘイズ / Purple Haze
6. アイ・シャル・ビー・リリースト / I Shall Be Released
オルケスタ・リブレ~plays standards Instrumental version / Can't Help Falling In Love ~ 好きにならずにいられない
【Track List】 1. 首の差 / Por Una Cabeza
2. ハッシュ / Hush
3. パープル・ヘイズ / Purple Haze
4. 小さな願い / I Say A Little Prayer
5. 遥かなる影 / Close To You
6. ハロー・ドーリー / Hello Dolly
7. シシリアンのテーマ / Le Clan Des Siciliens
8. 砂の岬 / Ponta De Areia
9. 好きにならずにいられない / Can't Help Falling In Love
アルバム発売によせて沢山のアーティストからコメントが届きました。
ブレヒトとクルト・ワイルの仕事は忘れてはならない財産。それが甦ってきた。これはやり甲斐のある音楽的な仕事だったに違いない。ブレヒトの「今日の世界は演劇によって再現できるか」という演劇論集の中に、「身振り的音楽について」というのがある。身振りとは、手の動きではなく、全体的態度だという。これに注意することによって、音楽家は政治的態度を音楽によってはっきり示すことができるようになる、と言う。オルケスタ・リブレが選んだ音楽に必要な身振りは、細心の心配りではないか。湯気の出るような新鮮さにして、すでに名盤の薫りを放っている。巻上公一
>>サエキけんぞう、谷川俊太郎など、全アーティストから届いたコメントはこちらから
OTOTOYスペシャル企画!! 芳垣安洋による全曲解説!!

うたのかたち ~ UTA NO KA・TA・TI〜オルケスタ・リブレと柳原陽一郎

1. Alabama Song
ベルトルト・ブレヒトの舞台演劇「マハゴニー市の興亡」の挿入歌で、酒とお金が欲しいという人間の欲望を赤裸々に歌ったブレヒト=クルト・ワイルの曲。ドアーズ(The Doors)のファーストにも入っていて、ドアーズが選んだのがぴったりという感じがしますね。我々も、実生活はドアーズとはかけ離れていますが、猥雑さと混沌と快楽とが混ざり合う、そんな世界観を表現してみました。本当は1番にあたる歌詞なんですが、3コーラスめに、実は、私が拡声器でかぶせてみました。コーラスはもちろんバンド全員で。これはヤナちゃん(柳原陽一郎氏)の歌ではありません。くれぐれもお間違いなきように。
2. ジゴロのバラード
で、ここからはブレヒトの代表作でもあり、クルト・ワイルが20代で作り上げた傑作曲の宝庫といえる「三文オペラ」の中から、3曲立て続けに並べています。まずは、主人公メッキー・メッサーが警察に捕まりそうになって昔の恋人のところへ逃げ込んだときに、二人の思い出を歌でかわすシーンです。しかも恋人は娼婦、逃げた先は娼館。何ともすごい歌なんですが。ヤナちゃんにかかるとなぜか、人間の切なさと温かさが伝わってくるのです。演奏は抑えながらも、20世紀初頭のはねたラテン・アメリカを意識して、ちょっとパンクとキング・クリムゾンを振り掛けてみました。
3. モリタート
「三文オペラ」の冒頭、メッキー・メッサーがいかに凄いワルなのかを狂言回し役が歌うのですが、それも実は噂だけで、ほんとは気の小さなただのプチブルを気取った似非紳士であることがわかってきます。でもやはり歌詞はどぎついですね。この歌、よくCMや番組のタイトル・バックで使われていますが、ほんとはこんな内容の歌なのですよ。ジャズ・ミュージシャンもよく取り上げていますが、やってる人も聴いてる側もわかってるのかなって心配になりますよね。これだけ実はライヴのテイクなんです。ここに本当は入るはずだった楽曲が日本語への訳の許諾がおりなかったので、入れられず、急遽ライヴの音源からの収録となりました。ここで使われているちょっとひねったコードは、3年前に、私、青木タイセイ、高良久美子、塩谷博之さんも参加した、宮本亜門さん演出の「三文オペラ」で音楽監督だった内橋和久が考えたものをもとにしています。
4. 「三文オペラ」第2のフィナーレ
2幕のフィナーレにこれが歌われるのですが、出演者が次々に交代で、それぞれの生活を脅かす敵ともいえる階級に向かってアジテーションっぽく歌います。ここではメロディーは我々が演奏し、ヤナちゃんにはブレヒトの戯曲をもとに彼が膨らませたテキストを朗読してもらいました。これは本邦初公開だと思います。「食い物を」「銃を」と過激に言葉を投げていきますが、「本当に考えなくてはいけないことは?」「本当にしなくてはいけないことは?」と、今生きている自分たちを振り返ることのために投げかけているんじゃないですかね。タイセイのアレンジもテキストにマッチして一層言葉が際立ってきます。
5. Ev’rytime We Say Good Bye
この曲は、ジョン・コルトレーンとレイ・チャールズのアレンジの方が好きです。昔、カルメン・マキさんと一緒にやっていた頃、彼女がこの曲を日本語で歌いました。詩があまりに素敵で驚いたのですが、其の訳詞がヤナちゃんだったのです。いつか彼とこの曲を、彼の詩で一緒にやるのが夢でした。ボサノバでやりたい、といった私のリクエストに応えた鈴木正人のアレンジもこんなにも素晴らしい事になっちゃって。言うことなしですね (本当は、スタイル・カウンシルみたいにしてくれ、といったのですが、さすがにそれは却下でした)。
6. Alfie
で、ここで一息。チェイサー代わりにバンドでバカラック・ナンバーを。ほんとは、収録されるはずだった曲と呼応した選曲なんですけどね。 見ているとちょっと寂しい気持ちになる、おしゃれを貫く現代のジゴロを主人公にした映画のテーマ曲です。 これは、パート・バカラックのインスト版に準じた展開にしてみました。金管楽器のハーモニーがちょっと切なくありませんかね。いつもは支えに回っているギデオンのチューバがメロディーを奏でると、特にそんな気がします。
7. Smile
チャップリンが『モダンタイムス』の中の挿入曲として作曲したものに、後から詩をつけたものが一人歩きしてしまったという曰くの曲です。あちらでは、マイケルまで歌ってましたね。でも我々は、このヤナちゃんの詩で、元気づけられています。日本語で歌ってもらったのが本当によかったなって思える曲になったと思います。タイセイのアレンジもなんか少し懐かしい気がしませんか。 というところで柳原サイドのアンコールはこれにて終了です。
うたのかたち ~ UTA NO KA・TA・TI〜オルケスタ・リブレとおおはた雄一
1. 愛しのセシリア
サイモン&ガーファンクルは、小学6年のときに「アメリカ」という曲で始めて聴きました。なんだか都会的で日本のフォークと違うなあと思ったものです。我々の年代はほとんどが彼らのいろんな曲を知ってると思うのですが、なかでもなにかパーカッシブで明るい曲がないかなと思っていたらこれに至りました。ポール・サイモンがオープニングでオロドゥンと一緒にやっていたセントラルパークのコンサートは今でも好きで、同じようにサンバヘギっぽくやってみました。ほかの曲はほとんどオーバー・ダビングをしなかったのですが、この曲だけはパーカッションを結構重ねました。
2. ゴロワーズを吸ったことがあるかい
おおはた雄一と出会ってから、弾き語りの人とやることが楽しくなりました。今では二人きりで、何の曲をやるかも全く決めずにライヴをやることもあります。もちろんバンド形式でも一緒にやってます。そんな彼のレパートリーの中でもとりわけ激しい感じでやっていたのがこの曲でした。面白いレパートリーだなってずっと気になっていて、この企画を思いついたらすぐに、この曲をやらないかって持ちかけてみました。ムッシュかまやつさんの原曲は、なんとタワー・オブ・パワーがバックを務めています。我々も少し其のテイストをだしてみようか、ということで、大輔に低いところでリフを入れてもらったりしていますが、鈴木正人のアレンジでのリブレのホーン・セクションは、またこれはこれでひけをとらない独自のサウンドなんですよ。
3. リリー・マルレーン
時々おおはたが弾き語りでもやる曲です。彼の選曲は30代の感覚じゃない気がします。歌を普通に歌うと、あっという間に終わってしまいます。さてどうしようかとなったのですが、この曲が第一次世界大戦のときに敵味方の別関係なく親しまれたという有名な話から、何となく軍隊の行進のイメージが浮かんできました。さらにさかのぼって、トルコの軍楽隊のような一団が遠くからだんだんと行軍して近づいてくる、というようなことを思い描いてタイセイにマーチを作ってもらいました。「青い旅団」のマーチと名付けた曲がかすかに響き、左から右に、そしてどんどんと押し寄せてくる間にも、ステージではリリー・マルレーンが歌われ続けているのです。
4. オー・シャンゼリーゼ
これって元々イギリスの曲なんだそうです。知ってました? 何となくこの曲のメロディーがフランスっぽいと思ったフランスの詩人が、勝手にパリの町の歌にしてヒットさせてしまったそうです。今までだまされてましたね。いつもおおはたがライヴのときにちゃかすのですが、この歌詞はほんとにとんでもないですね。そんな簡単に恋人同士になれるのでしょうかね。なんてことは言わないで、楽しくやりましょうって、アート・アンサンブル・オブ・シカゴがブリジット・フォンテーンとやった「ラジオのように」みたいなシャンソンをやろう、っていう合い言葉だけでやったら、こうなってしまいました。 たらいはスタジオ中引きずり回しました。
5. Purple Haze
この曲は、最初はブランドン・ロスと一緒にやろうと思って選曲しました。彼が、ジミヘンみたいには絶対できないからやり方を考えてくれ、といったので、鈴木正人といっしょにこんな風にバンドだけのベーシックを作ってみました。結局、彼と引き続き作業をする時間がなく、お蔵入りになりそうだったのですが、とりあえずナベちゃんにラッパで歌ってもらったら、非常にいい感じで、インスト・バージョンが出来上がりました。ベーシックを聴いていると、こりゃあおおはたが歌ってもいいんじゃないかなって気もしたので歌ってもらったら、この不思議なパープル・ヘイズができた次第であります。アルバムの中、唯一英語というのもちょっとアクセントになっていると思います。おおはたにアコースティック・ギターで、椎谷にペダル・スティールで絡んでもらったら、ルンバの太鼓となじんでいい色合いになった気がします。
6. I Shall Be Released
ご存知、ボブ・ディランのそしてザ・バンドのヒット曲です。これは、岡林(信康)さんから(忌野)清志郎さんから、いろんな人がみんなそれぞれの歌詞をつけて カバーしています。今まで、おおはたは、彼自身の曲の最後にメドレーで、しかも英語で歌っていたのですが、フル・コーラス、しかもおおはたの意訳の詩でやってほしいとおねがいしました。今回のシンガー二人に共通するのは「素晴らしい詩人」であること。先輩たちの訳に負けない素敵な歌になりました。で、これは私のわがままで、レゲエにしてもらいました。「新宿2丁目のスライ&ロビー」と異名を取る(?)私と正人の出番というわけです。益子樹が施してくれた、クラリネットのソロを彩る不思議なダブも効果的でしょ。
こうしてステージが幕を下ろすことになります。
Can't Help Falling In Love ~ 好きにならずにいられない

1. Por Una Cabeza 首の差
19世紀後半に生まれたといわれるタンゴの世界で、そしてアルゼンチンで今もなお崇拝される、歌手、作曲家、映画俳優といくつもの顔を持つ大スター、カルロス・ガルデルのヒット曲の一つ。普通は「首の差で」「頭の差で」と訳されてます。恋の駆け引きにちょっとの差で負けた事を、競馬に掛けて歌った曲ですね。いろんな局面が展開して、メンバーが入れ替わりいろんな組み合わせでフィーチャーされるアレンジになっています。局長も含め、我々のオープニングにはもってこいだと思います。
2. Hush ハッシュ
私が高校生の頃にハード・ロックといえば…と代名詞の一つになっていたディープ・パープルのデビュー作のタイトル曲。ずっとパープルの曲だと思ってたんですが、そうでなかった事のこの歳で初めて気がつきました。クーラ・シェイカーのもかっこいいですが、パープルのはジョン・ロードのオルガンがガコンガコンしてて何ともカッコいいんです。私と岡部はブラジルのマラカトゥとファンクをミックス。1、2曲目は、タイセイのアレンジによる管楽器の絡みがキモですね。民族音楽的な雰囲気もあるでしょ。
3. Purple Haze パープル・ヘイズ
皆様よくご存知、ジミヘンのヒット曲です。最初は、NYのギタリスト、シンガーのブランドン・ロスに歌ってもらう事を想定してアレンジして、バンドの方だけは先に録音したのだけれど、リリースまでに歌をいれる時間がなくなってしまい(来日が延期になってしまったため)急遽、おおはたに歌ってもらうバージョンとインスト・バージョンとの二つを作ってみて選ぶ事にしたのですが。どちらもいい。おおはたの歌の雰囲気も、ナベちゃんのラッパも最高。で、どちらもいれることにしました。原曲と全く違う雰囲気を出すために3拍子で始まって、最後はルンバにしたいと言ったら、鈴木正人がこんなに怪しくしてくれました。
4. I Say A Little Prayer 小さな願い
大好きなバカラック・ナンバーです。いろんな人が歌ってますが、これはソウルの女王アレサ・フランクリンのうたったバージョンを意識してます。なので、で(藤原)大輔がアレサだと思って聴いていただけたらと思っています。トム・ジョーンズの番組に出演したときの映像がDVDになってるんですが、これは逸品です。何せバカラックの曲はいろんな人がいろんなやり方でやっているので聴き比べる楽しみもありますね。我々のこれも加えていただければうれしいです。
5. Close To You 遥かなる影
これもバカラック・ナンバーですが、この曲はカーペンターズを思い出す人がほとんどでしょうね。私もどうしてもカレンの声とあの演奏が頭にこびりついてはなれなかったので、どうしようかと思ったのですが、どうしてもやりたかったので、この様に一旦解体してみました。ナベちゃんと塩谷さんの音が、バカラックの、いやハーブ・アルパートがトランペットを吹くアンサンブルと同じ響きを聴かせてくれたのにも驚きです。
6. Hello Dolly ハロー・ドーリー
私は、トランペットが好きだという事もあるのですが、なんと言ってもサッチモが一番好きなジャズ・ミュージシャンです。音楽をそして周りの人を楽しくする要素をすべて持っていたホントにすばらしい人だったと思います。しかも即興で人々を引きつける力の大きさはただ事じゃないですよ。これはそんな彼の代表曲ですよね。バーブラ・ストライサンドと映画の中でこの曲で絡むシーンも最高!!そしてもう一人、この曲を演奏している人で忘れてはいけないのが、敬愛するレスター・ボウイ。レスターとジョン・ヒックスのデュオ、アート・アンサンブル・オブ・シカゴ、疾走するサッチモ楽団の三つの表情を出してみたかったのです。
7. Le Clan des Siciliens シシリアン
子供の頃、テレビの洋画劇場でみたジャン・ギャバンとアラン・ドロン。意味がよく分からないところもあったのですが、何とも荘厳で、怖くて、悲しくて、渋くて、といったイメージがずっと残っていました。このようなフィルム・ノワールといわれたフランスの映画が私の子供の頃流行ってましたね。そしてどの映画にも不思議な雰囲気の曲が添えられていました。エンリオ・モリコーネは本当にいろんな映画作品で名前をみますね。いつか彼の関わったマカロニ・ウエスタンものをやってみるのも夢です。このテイクでは、大輔のソロはもちろんなんですが、椎谷(求)のペダル・スティールと高良のヴァイブ、そしてタイセイの鍵盤ハーモニカをフィーチャーしています。
8. Pont De Area 砂の岬
大学4年のときにがっつりとはまってしまったミルトン・ナシメント。 ウエィン・ショーターのネイティブ・ダンサーというアルバム、ミルトン自身のミナスというアルバムが私の原体験でした。これも元はブランドンとレコーディングしたのですが、ミックスができないままでした。どうしても入れたかったのでインストで挑戦してみました。タイセイのポップな和音のセンスが原曲とは違った味わいを出していますね。最後の塩谷さんにはぐっとつかまれました。
9. Can’t Help Falling in Love 好きにならずにいられない
プレスリーですよ。やっぱり。聴き直してみるとホントに彼はいい声してます。若い頃はあまりにも格好良すぎて、そりゃあ女の子も失神するでしょうよ、と今では悔しさはおいておいて、純粋に思えるようになりました。そしたら無性にこの曲がやりたくなりました。UB40のレゲエもよかったので、それも考えたのですが、とりあえずリズムが変化し交錯しながらどんどんと盛り上がっていくのが面白いんじゃないかと思って。タイセイが途中に作ってくれたアフリカン・テイストのリフもパンチが効いてます。放し飼い状態の岡部もとどまるところを知らず。その中でひたすら3拍子と4拍子を同時に演奏していると、もう気持ちよくて、ちょっと危険で、仕方ありません。アルバムのラストを飾るのにふさわしい演奏になったと思います。
これぞ生の醍醐味!! Orquesta Libreのライヴ音源をHQDで独占配信中!!
2012年2月5日 Orquesta Libre with おおはた雄一 @新宿PIT INN
「さまざまなジャンルのスタンダード・ナンバーを片っ端からやってみる」。そうしたコンセプトを掲げ自由でのびのびとした演奏を聴かせる大所帯バンド、Orquesta Libreが、2012年2月5日に新宿ピットインで、おおはた雄一を迎えてライヴを24bit/48kHzのHQDで配信中。ブルースやフォーク・ミュージックをルーツとするシンガー・ソングライターおおはた雄一と、芳垣安洋率いるOrquesta Libreが、スタンダード・ナンバーという一つの目的に向かって曲を奏でる緊張感溢れるライヴをお楽しみください。
Orquesta Libre with おおはた雄一 / Plays Standards vol.1 -LIVE at PIT INN 2012.02.05- (HQD ver.)
【配信形態】 HQD(24bit/48kHz WAV)
【価格】
1500円(まとめ購入のみ)
<Track List>
01. Por Una Cabeza(首の差 ) / 02. Hello Dolly / 03. Ponta De Areia / 04. One Morning / 05. リリー・マルレーン / 06. ひとりにしてくれ / 07. オー・シャンゼリゼ / 08. Purple Haze / 09. ゴロワーズを吸ったことがあるかい / 10. Misterioso
>>芳垣安洋とおおはた雄一の対談はこちら
2012年4月17日 Orquesta Libre with柳原陽一郎@新宿PIT INN
Orquesta Libreが、2012年4月17日に、柳原陽一郎をゲストに迎えて行った、新宿ピットインのライヴを高音質HQDで配信! 「Alabama Song」や「三文オペラ第二のフィナーレ」といった往年の名曲が、柳原陽一郎の対訳とヴォーカル、そしてOrquesta Libreの演奏によって、迫力のあるアレンジで甦ります。
Orquesta Libre with 柳原陽一郎 / Plays Standards vol.2 -LIVE at PIT INN 2012.04.17- (HQD ver.)
【配信形態】 HQD (24bit/48kHz WAV)
【価格】
1500円(まとめ購入のみ)
【Track List】
1. こうてい / 2. 墓穴からの叫び / 3. Alabama Song / 4. 三文オペラ第二のフィナーレ / 5. Good-bye Poke pie Hat / 6. 4in 1 / 7. 恋のおもかげThe Look Of Love / 8. Me Japanese Boy / 9. 夢であいましょうi’ll see you in my Dream / 10. Ev’ry Time we say goodbye
>>芳垣安洋と柳原陽一郎の対談はこちら
芳垣安洋とおおはた雄一の2人だけのセッションを記録したDSDライヴ音源も配信中
数々のジャズ・ミュージシャンとのセッションをはじめ、ROVO、渋さ知らズ、さらには自身が率いるVincent Atmicus、Orquesta Nudge! Nudge! など、幅広いフィールドで活躍する芳垣安洋。毎年恒例となった新宿PIT INNでの芳垣安洋4DAYSの初日6/21(火)に、おおはた雄一が登場。何を演奏するかは本番まで全く決めず、おおはた雄一がその時のフィーリングによってギターを弾き始め、芳垣が即興で合わせていくというスペシャル・セッションをDSDで録音しました。その中からおおはた雄一が選んだ全13曲をOTOTOY独占配信中。
芳垣安洋×おおはた雄一 / LIVE at 新宿PIT INN 2011.06.21
【配信形態】
1) DSD+mp3(320kbps)
2) HQD(24bit/48kHz WAV)
【価格】
各1500円(まとめ購入のみ)
【Track List】
1. 不思議なくらい / 2. キリン / 3. Prayer / 4. きみはぼくのともだち / 5. 決別の旗 / 6. ゴロワーズを吸ったことがあるかい / 7. 旅の終わりに / 8. おだやかな暮らし / 9. Good night, Irene / 10. Canción Mixteca -encore 01- / 11. トラベリンマン -encore 02- / 12. He was a friend of mine -bonus track- / 13. サカナ -bonus track-
INFORMATION
Orquesta Libre
Orquesta Libre European Tour 2012
http://www.jvtlandt.com/orquestalibre/
2012年7月11日(水)@The Vortex, London, UK
http://www.vortexjazz.co.uk/
2012年7月13日(金)@Copenhagen Jazz Festival, Denmark
http://locomusic.dk/koncerter/orquesta-libre-jp-selvhenter-vand%E2%80%A2pi%E2%80%A2stol-feat-j-spliff-pauloverb-inckhaleren/
2012年7月14日(土)@Passau, Germany
http://www.cafe-museum.de/index.php?option=com_content&task=view&id=500&Itemid=593
2012年7月18日(水)@IKuR, Bern, Switzerland
http://www.reitschule.ch/reitschule/index.shtml
2012年7月19日(木)@La Barje Des Sciences, Geneva, Switzerland
http://www.labarje.ch/
FUJI ROCK FESTIVAL’12
2012年7月29日(日)@新潟県湯沢町苗場スキー場場 ORANGE COURT 出演
芳垣安洋 ライヴ・スケジュール
2012年7月25日(水)@横浜JazzSpot DOLPHY
2012年7月28日(土)@新潟県湯沢町苗場スキー場場
2012年7月29日(日)@新潟県湯沢町苗場スキー場場
2012年8月3日(金)@江古田Buddy
2012年8月5日(日)@横浜JazzSpot DOLPHY
2012年8月6日(月)@西宮Jazz Spot Corner Pocket
2012年8月7日(火)@梅田シャングリラ
2012年8月8日(水)@今池TOKUZO
2012年8月11日(土)@石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
2012年8月14日(火)@代官山 晴れたら空に豆まいて
2012年8月18日(土)@横浜サムズアップ
PROFILE
Orquesta Libre
日本を代表するトップ・ドラマー芳垣安洋(Vincent Atmicus, ROVO, ONJT, Altered States, Orquesta Nudge! Nudge!) が率いる、'60~'70年代のロックやポップス、演劇舞台音楽、ミュージカルや映画音楽、ジャズ・チューンから第三世界の 音楽まで、邦楽/洋楽のスタンダードソングを“うた”と“インストゥルメンタル”でプログレッシヴに再定義する、10人の楽団 員とゲスト・ヴォーカリスト2人からなる、どこか不穏でそのくせキュートなオルタナティヴ吹奏楽団!!!
〈メンバー〉
芳垣安洋(ds, perc, arr)
青木タイセイ(tb, key-harmonica, arr)
塩谷博之(ss, cl)
藤原大輔(ts)
渡辺隆雄(tp)
ギデオン・ジュークス(tuba)
高良久美子(vib, perc, key-harmonica)
鈴木正人(b, g, arr)
椎谷求(g, steel-g, mandolin, banjo)
岡部洋一(perc)
芳垣安洋
関西のジャズ・エリアでキャリアをスタートさせ、モダン・チョキチョキズ、ベツニ・ナンモ・クレズマー・オーケストラ、渋さ知らズなどに参加後上京。渋谷毅、山下洋輔、坂田明、板橋文夫、梅津和時、片山広明、巻上公一、ホッピー神山、大島保克、菊地成孔、オオヤユウスケ、高田漣、ヤドランカ、酒井俊、長谷川きよし、カルメン・マキ、おおたか静流、小島真由実、浜田真理子、カヒミ・カリィ、UA、原田郁子、Jhon Zorn、Bill Laswellなど様々なミュージシャンと共演。現在、ROVO、大友良英ニュー・ジャズ・オーケストラ、南博GO THERE、アルタード・ステイツや自己のバンドVincent Atmicus、Emergency!、Orquesta Nudge!Nudge!等のライヴ活動の他、蜷川幸雄や文学座などの演劇や、映画の音楽制作も手掛ける。メールス・ジャズ・フェスを始めとする欧米のジャズや現代音楽のフェスティバルへの出演や、来日するミュージシャンとの共演も多く、海外ではインプロヴァイザーとしての評価も高い。自身のレーベル「Glamorous」を主宰する。
芳垣安洋 official web
Orquesta Libre official facebook